芥川龍之介の著作『藪の中』。
藪で武士の男が遺体で発見され、その死因の聴取をする形で進む物語です。
しかし何故か当事者たちの意見は食い違い…?(殺された男の幽霊まで聴取可能なのに)
真実は藪の中なのか?
この記事では、簡単なあらすじと登場人物をまとめた後、犯人について考察していきたいと思います。
目次
あらすじを簡単に要約
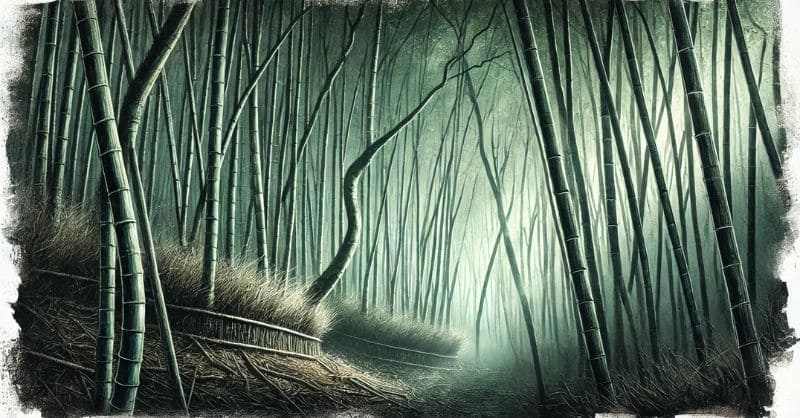
物語は、木こりが山中で男性の死体を発見する場面から始まります。
その後、旅法師、放免、被害者の妻、盗賊の多襲丸、さらには霊媒を通じた被害者自身の証言が続きます。
- 木こりの証言:今朝山中で男の死体を発見し、近くには縄と櫛が落ちていた。
- 旅法師の証言:前日に武士の男とその妻が一緒にいるのを目撃した。
- 放免(多襄丸を捕らえた捕り方)の証言:多襄丸を捕らえた際、被害者の持ち物と思われる武具を所持していた。
- 多襄丸の自白:被害者を殺害し、妻を手に入れようとしたが、妻は逃げたと述べる。
- 妻の証言:多襄丸に暴行された後、「自らの恥を見た」として一緒に死ぬことを提案する。しかし夫を殺害しても、自らの自殺には失敗。清水寺で懺悔していたと述べる。
- 被害者の霊の証言:妻が多襄丸と共に去った後、自ら命を絶ったと語る。しかし自らが刺した小刀を誰かが抜き、それを機に息絶えたと述べる。
【考察】犯人は誰?一番やり手なのは?

被害者(夫)を刺したのは誰なのか?
作中での主張をまとめてみるとこうです。
| 人物 | 主張 |
|---|---|
| 多襄丸 | 決闘の末、自分が男を殺したと述べている |
| 妻 | 夫婦そろって自殺を提案。夫の同意も得て自分が殺したと述べている |
| 夫 | 自ら小刀で胸を刺して命を絶ったと述べている。 |
全員が全員、「自分が殺しました(自死しました)」と供述する異常事態。
しかもこれは、「推理すれば嘘つきの二人が判明して一人に絞れる」というものではありません。
『藪の中』が発表されたのは1922年(大正11年ですが)、現在も犯人は特定されておらず、読者の想像にゆだねる形になっています。
なぜ三人の供述が食い違ったのか?これは
- 修羅場下での混乱で思い違いをしている
- 自分の都合の良いように、嘘をついている
- 誰かを庇っている
などの理由が考えられます。
しかしながら三名の供述全てが食い違っているわけではなく、「主観が違うだけで、この人のこれとこの人のこれは同じエピソードを指しているのでは?」というものも沢山。
ここがこの物語の面白いところです。
ここからは「一番の悪人は誰か?」ということを真実と虚像を照らし合わせながら、個人的な考察をしていきたいと思います。
死人を出したのは妻

夫を刺した犯人については分かっていません。
しかしこの事件が暴行事件から殺人事件に変化したのは、間違いなく妻の言動があったからでした。
多襄丸は過去に殺人歴もある男でしたが、この一件では「男を殺さずに女を手に入れる」ということに、確かに成功していたのです。
そして逃げようとしたーー……このまま去れば暴行事件でした。
しかし、それを妻が止めました。
- 多襄丸の供述:女が腕に縋りついてきて「あなたか夫、どちらか一人死んでくれ。二人の男に恥を見せるのは死ぬよりもつらい。生き残った男につれ添いたい」と切れ切れに叫んだ。
- 夫(被害者)の供述:妻は多襄丸に「妻にならないか」と言われて同意した後、「夫を殺して下さい。夫が生きていては、多襄丸と一緒にはいられません」と気が狂ったように、何度も叫び立てた。
これは、多襄丸と夫の証言がほぼ合致していると言ってよいでしょう。
ニュアンスが違いますが、要するに
- 私の恥を見るのは夫だけだ。もう一方は死んでくれ
と訴え、それがきっちり二人の心に刺さった故に殺人が起こった…ということです。
ちなみにこれについて妻はなんと供述しているのか?
我知らず何か叫んだぎり、とうとう気を失ってしまいました。
黒っぽいですね。
覚えていないというスタンス。
さも自分の意志ではないような、気がふれて何かを言ってしまった的なニュアンスも出しています。
そもそもなぜそんな言い方をしたのか?
夫は完全なる被害者なのに、多襄丸に「お前を殺してやる!」ではなく「どちらか一方が死んで」。
この言葉を発した妻の人間性についても考えていきましょう。
妻『真砂』の人間性。貞操観念か復讐かそれとも

妻は非常に貞操観念(夫以外に体を許してはいけないという考え)が強い女でした。
それは妻の父親が「夫のほかには、男を持った事はございません」とわざわざ供述していることからも分かります。
だからこそ、夫の「多襄丸の言うことを真に受けるなという目くばせ(夫本人談)」を
「暴行を受けた自分(夫以外に体を渡した自分)を蔑んだ目」だと考えてしまいました。
この勘違いがショック過ぎた結果「どっちか死んで(意訳)」と半狂乱になって叫んだーーー……
という考え方もできますが、本当にそうでしょうか?
- 自分に暴行を加えた多襄丸
- 多襄丸の嘘にまんまと騙され、武士の癖に妻が暴行を受けることも阻止できない無能な夫
両方に殺意を持って、どうせなら殺し合わせようとした……ということも、考えられるかもしれません。
夫・妻を藪の中に引きずり込んだ経緯については多襄丸しか語っていません。
よって彼の言い分を信じることになりますが、
夫は多襄丸の「おいしい話」にまんまと食いついた馬鹿で、妻は最初から警戒した利口な女でした。
多襄丸に声をかけられた妻の行動▼
- 藪に入らず馬に乗ったまま待つ(警戒?)
- 市女笠を脱いだまま(視界が狭くなるのを防ぐため?)
- 小刀を持ち、縛られた夫を見てすぐさま攻撃
となれば、もし暴行後に多襄丸が逃げ、夫が妻に軽蔑をいだかない比較的平和な終わり方をしたとしても……
妻から夫への愛は冷めてしまったのではないでしょうか?
かといって貞操観念が強い女ですから、「浮気をしよう」とはならないでしょう。
つまり「情けない男が唯一の自分の男」なのです。
こんなどん詰まり状態を回避するために妻から出た言葉が、
多襄丸の供述にあった「生き残った方に連れ添いたい」であれば……
勝気な人物像がきっちり当てはまると思います。
ここで夫が多襄丸に勝てるのであれば、夫への愛情も戻ってくるかもしれませんしね。
妻はなぜ「自分が殺した」と言ったのか?

では上の考察が当たっているとすれば、何故妻は「夫は自分が殺した」と供述するのか?
(正しくは、一緒に死のうとして自分は死ねなかった)
これは「どちらかを殺してくれ」という発言が多襄丸から漏れることを考え、「漏れても他人から同情される実績」を作ろうと考えたため……ではないでしょうか?
その実績というのが「自殺失敗」です。
妻はこんなことを言っています。
小刀
を喉
に突き立てたり、山の裾の池へ身を投げたり、いろいろな事もして見ましたが、死に切れずにこうしている限り、これも自慢
にはなりますまい。
つまり、「実際に自殺すれば自慢になる」という価値観を、妻は持っていたのです。
現代では中々同意できない価値観ですが、具体例があります。
なんと、芥川と同じ時代を生きた文豪「太宰治」が似たようなことをやっているのです。
恋人と心中して自分だけ助かった太宰は咎められておらず、一種の武勇伝のように扱われていました。
(下記の実話を元にした映画で見ました)
この先も未来ある「妻」。もしかするとこれは、お涙頂戴シナリオだったのかもしれません。
一番信用できるのは誰?

最後にメタ的に考えてみましょう。
食い違う三人の意見にはどのようなフィルターがかかっているでしょうか?
これを念頭に置いたうえで『藪の中』を読むと、とても面白いです。
まず一番信用できるのは、被害者である夫です。
- 被害者の夫……妻の発言が衝撃的なため妻を恨み、多襄丸のことはそこまで恨んでいない。
武士であるため自分の情けないところ(刀を交えて負けたなど)があれば隠そうとするだろうが、死んでいるので自己保身する理由はほぼ無い。
次に多襄丸です。
- 多襄丸……捕まった時点で死刑は確定なので、保身する理由は殆どない。
しかし役人に対しての恨みから混乱させるようなことを言ったり、「女を妻にしたい」という発言には信憑性も見られるため庇う可能性がある。
そして一番信憑性が薄いのが妻です。
- 妻……この一件が一番未来に影響するため、できる限り被害者でいきたい。
故に自分の都合の悪い箇所を「暴行されて発狂した」「気を失った」で誤魔化している節も見える。
いつの間にか姿を消している部分の言動が不明。
つまり事件の発端を起こしたのは多襄丸ですが、
暴行後の状況を一番うまく自分本位に説明したのは妻なのではないか……?
そのように思えます。
まとめ

『藪の中』の犯人についてまとめると……
- 殺人犯については判明していない。
- 当初は暴行事件だったが、殺人事件になったのは妻の言動がきっかけだった。
- 事件は「多襄丸」が捕らえられ、彼が自白しているためその方向で片づけられると見られる。
- 妻は貞操観念や復讐心をいだき、殺し合いを望んだかもしれない。
- 一番信用が置ける供述は、死んでしまった夫の霊。
ということでした。
とても面白いので、是非読んでみてください!
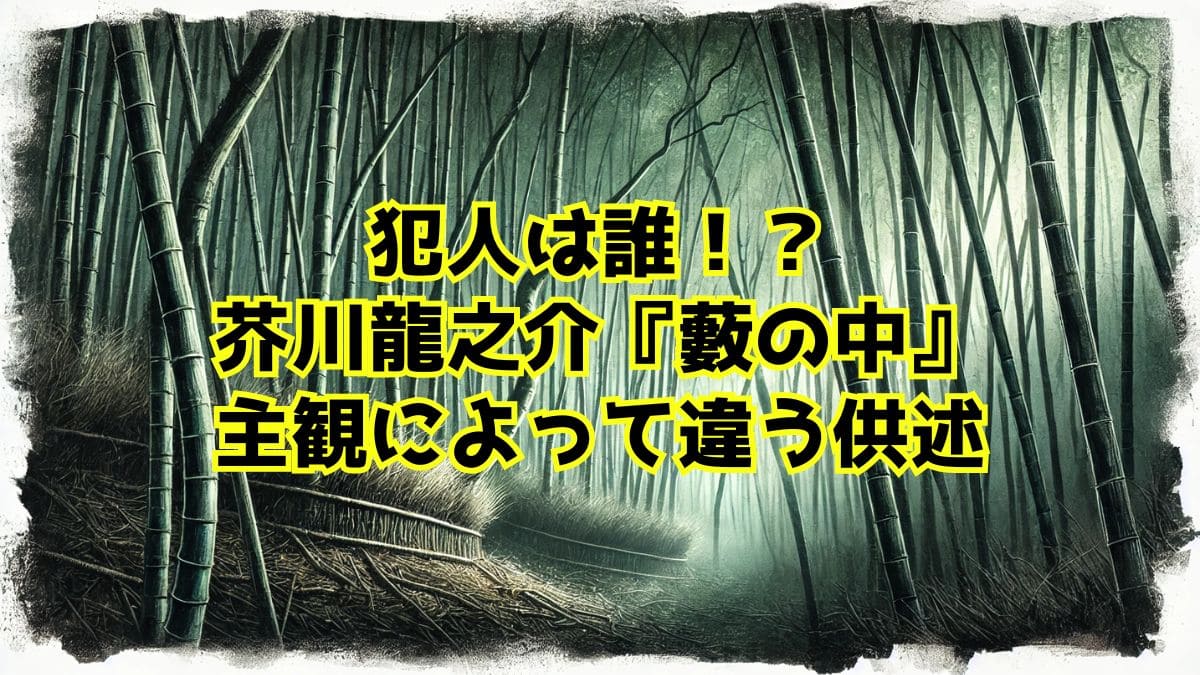










コメント