執事が、執事としての役割を離れて良い状況はただ一つ、自分が完全に一人だけでいるときしかありえません。
この記事ではカズオ・イシグロの著書、『日の名残り』について
- あらすじ・登場人物
- 何故「つまらない」という意見があるのか
- 個人的感想
をお伝えしていきます。
イギリスの栄誉ある文学賞『ブッカー賞』を受賞した、とある執事の物語です。
目次
あらすじ

イギリスのダーリントン・ホールに長年仕えてきた執事、『スティーブンス』。
前の主人である『ダーリントン卿』が亡くなってから三年。
今はアメリカ人の『ファラディ様』に仕えている。
スティーブンスの最近の悩みは、ファラディ様の求めるジョークを返せないことと、仕事にミスが増えていることだった。
そんなある日、1カ月以上屋敷を離れるファラディ様から「君も羽を伸ばしてきてはどうか?」と提案された。
乗り気ではなかったスティーブンスだが、かつてしのぎを削ったメイド長…『ミス・ケントン』から手紙がきたことで気が変わる。
ミス・ケントンが現状に満足していないなら、復職させることはできないか……?
また一緒に働ければ、職務計画も完璧なものになる。
スティーブンスは数日間のドライブ旅を決めた。
この物語では、ミス・ケントンと会うまでの6日間の旅路、そしてミス・ケントンと働いた頃の思い出が語られる。
- 「執事の品格」とは何か?
- ダーリントン卿に仕えた日々
- 死んだ父について
- ミス・ケントンとの思い出
職務を離れて昔を思い出した、スティーブンスの思うこととは…?
そしてミス・ケントンの答えは…?
タイトル『日の名残り』の意味

タイトル『日の名残り(ひのなごり)』はどこから来ているのか?
これは『ダーリントン卿に仕えた日の名残り』で間違いないでしょう。
名残りは余波とも言います。あの日の余波を旅路の中で追い求めるスティーブンス。もう過ぎ去った緊張感ある日々を思い出して考える。
そんなこの物語にぴったりの名前だと思います。
主な登場人物

主人公:スティーブンス……『品格』ある執事になりたい、ダーリントン・ホールの老執事。
前主人:ダーリントン卿……以前の雇用主。館に諸外国の重要な人物を招き、政治に影響を与えていた。
現主人:ファラディ様……現雇用主。アメリカ人。自分が屋敷を離れる期間、スティーブンスに旅行を提案する。
以前の同僚:ミス・ケントン……スティーブンス全盛期に一緒に働いたメイド長。現在は結婚しているが…
簡単な感想

誇りある英国執事の物語。「イギリスの栄誉ある文学賞」であるブッカー賞に選ばれるのも頷ける内容です。
本場の執事業、メイド業が知りたい方は一度読んでみても良いのではないでしょうか…?
職務を完璧にこなすだけではなく、「品格ある」執事を目指して考え続ける主人公。
とんでもなく意識が高い系ですが、主人に傾倒したからこそのつらい別れや、プライベートを疎かにした後悔もあって…という人間ぽさも垣間見える人物です。
また、「英国執事」と言うと別世界の話のように聞こえますが、仕事に関する自己啓発や、噂話への向き合い方なんかは現代人に通ずるところがあります。
計画の重要性とか、アンチに関するマインドとか……今と同じですね。
何故「つまらない」という意見があるのか

「日の名残り」で検索すると、第二検索ワードに「つまらない」という言葉が出てきます。
これについて、確かに個人的に腑に落ちるところもあるので記述いたします。
この作品は最初から最後まで、イギリスの老執事である『スティーブンス』の一人語りとなっています。
スティーブンスは珍しく旅に出ますが、初老の男ですのであまり目立つ行動には走りません。
回想の中では若い頃…スティーブンスの全盛期も出てきますが…
彼は「自分の自我を押さえつけて職務に励むのが執事の品格である」という考え方の為、せっかく盛り上がりそうな展開時も動きません。
せっかくの恋愛の気配が…!父が亡くなる転換期が…!この男、感情が分かりにくい…
兎にも角にも地味なのです。
俗っぽさを求める読者は、そこを「つまらない」と感じるのでしょう。
さらにこの物語は、疑問を感じず素直に読んでしまうと、面白さが半減してしまいます。
スティーブンスは「信頼できない語り手」と言われている

私も読み終わった後に知った話なのですが、主人公スティーブンスは「信頼できない語り手」と呼ばれているそうです。
『信頼できない語り手』とは、物語における叙述トリックの一つ。
語り手が独白に嘘を混ぜる(或いは悪気なく混ぜてしまう)ことにより、読者を混乱させる手法です。
正直私はスティーブンスを殆ど信頼しながら読み切りましたし、
これを聞いても同作者の『遠い山なみの光』のほうが信頼できない語り手だよなぁ…と思ってしまうのですが…
確かにスティーブンスは
- 昔のことを語っている(記憶があやふやな面も多い)
- 主人が悪名の中死したため、自分の権威を守るためにいささか都合よく語っている
ということで、周囲と何か「ズレ」を感じさせるのです。
スティーブンスの語りを鵜吞みにして読むか。
或いは「真実はどうだったのか?」と考えながら読むか。
前者で読んだ場合、『日の名残り』はかなり大人しい部類の話になってしまうでしょう。
ネタバレ感想

この物語の肝は
- 本物の執事の品格とは何か
- 元主人・ダーリントン卿はなぜ亡くなったのか
- ミス・ケントンとの恋はあったのか?彼女に会いに行って何か進展はあるのか?
- 今回のドライブでスティーブンスのプライベートが垣間見える瞬間はあるか?
ということ。そして其々の答えは残酷でした。
- 「ダーリントン卿は名誉を汚され、部屋で(おそらく)自死した」……そしてこれを見つけてしまったのがスティーブンスだった。
- ミス・ケントンは、スティーブンスと一緒になることを最良の人生と考えたこともあったけれど、現在は良い夫を愛することに切り替えている…
- 旅路の中で、「ただ主人を妄信していただけの自分には品格が無い」とスティーブンスは自覚する――…
けれど疲れたスティーブンスに前を向かせたのが「ジョークの練習」…つまり現当主の望みでした。これはエモいですよね。
イシグロ文学は、トータルすると悲しさに偏るにもかかわらず、最後は絶妙な具合で主人公が前を向く気がします。
今回も執事・スティーブンスらしい終わり方だと感じました。
まとめ
- 初老の英国執事『スティーブンス』の物語。
- 彼が珍しく職務を離れて、昔の同僚に会いに行く旅路が描かれる。
- タイトルの意味は「ダーリントン卿に仕えた過ぎし日の名残り」だと思われる。
- スティーブンスは職業柄感情を抑えがちなため派手な展開になりづらく、そこをつまらないと考える読者もいる。
- スティーブンスの嘘を見抜けないと淡々とした物語に見えがち
- 品格ある執事へのリアリティが高く、職務内容は読んでいてワクワクする世界観
気になった人はぜひ読んでみてください!
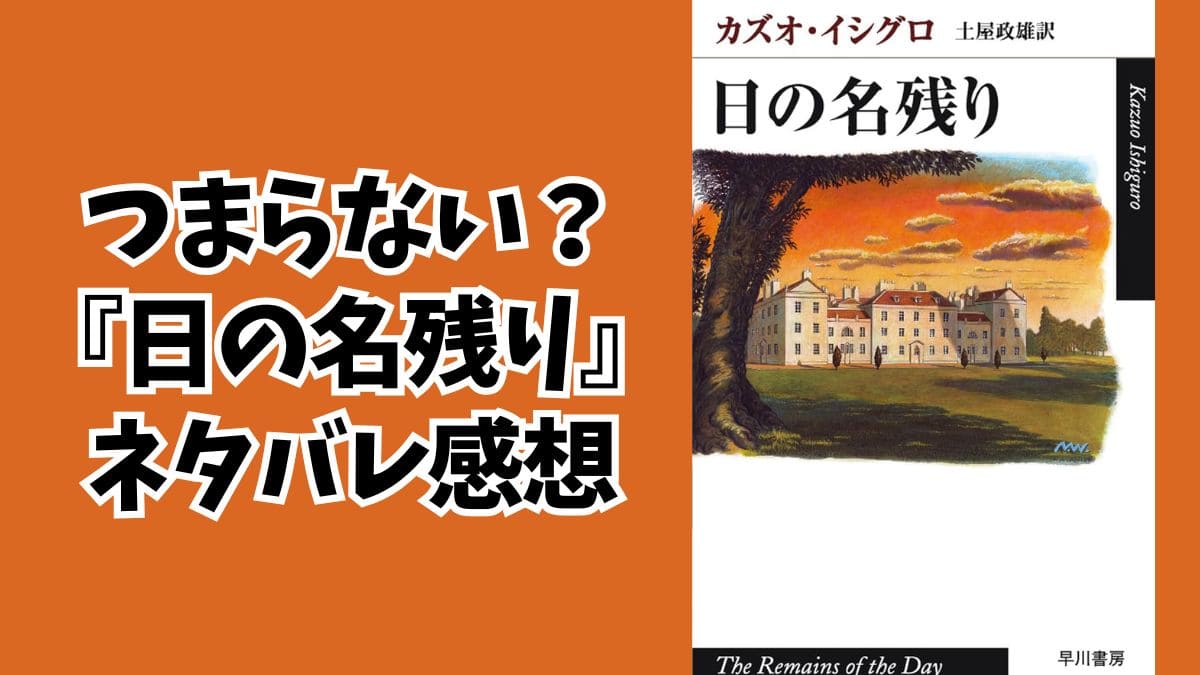
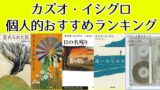


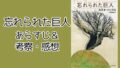
コメント